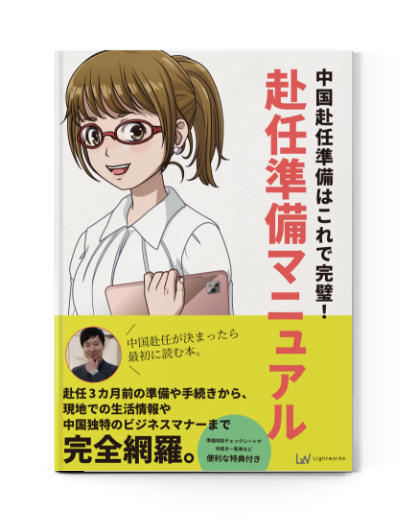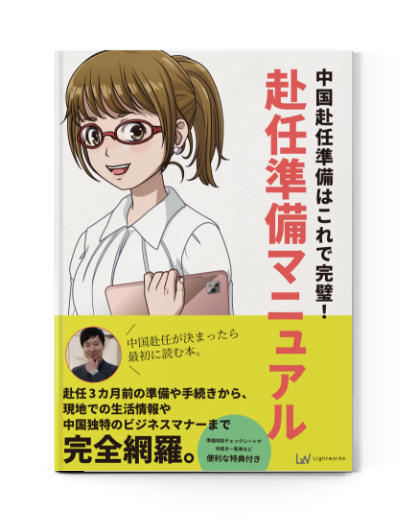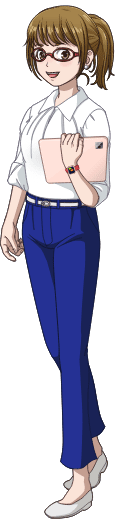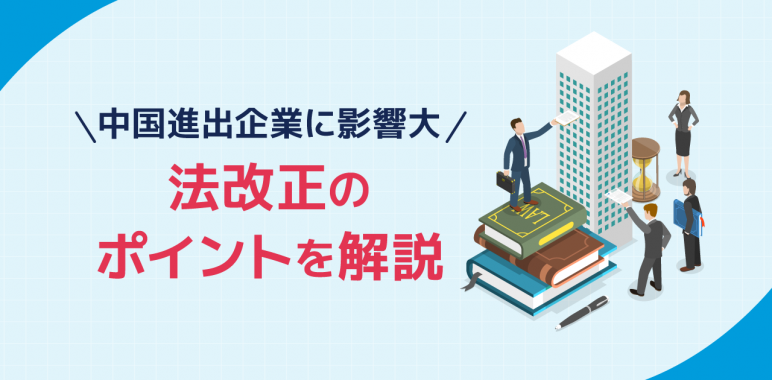「中国での商談やマネジメント。文化の違いによるトラブルを回避するためにも、ビジネスマナーを知っておきたい。」
郷に入れば郷に従えという言葉通り、文化の異なる地でビジネスをスムーズに進めるには、その地ならではのマナーを知ることが重要です。
中国人学生は一般的に、外国語の習得には熱心ですが、ビジネス上の国際感覚まで修めているかどうかは別問題。日本での普通や常識は、一切通用しないという心構えで、お互いの文化を理解して歩み寄ることで、円満な仕事関係に近づきます。
この記事では、現地ですぐに使える中国の基本的なビジネスマナーをメインに、実際に中国で働く日本人や中国人が在籍するライトワークスだからこそお伝えできる情報をご紹介します。
無料eBook
中国赴任準備はこれで完璧!
赴任準備マニュアル
事前の準備から現地の作法まで徹底解説
現地駐留歴4年のスタッフがまとめた渾身の一冊。
快適な中国ライフを送るための準備はこれで完璧!
目次
1. 中国におけるビジネスマナーのカギは「面子」
ビジネスマナーを知る前に、中国の特徴的な文化として「面子をとても大切にする」傾向があるということを理解しておいた方がよいでしょう。
日本でも、「顔が立つ」「面子にかかわる」「面目を保つ」など、面子を大切にする文化は健在です。しかし、中国での面子が持つ役割は、日本とは少し異なります。
中国では、「木に樹皮がなくてはならないように、人には面子がなくてはならない(人要臉、樹要皮(rén yào liǎn、shù yào pí))」という諺があり、自分の社会的存在や価値そのものと言っても過言ではないほど、とても重要な意味を持ちます。
中国人と仕事を進める上で直面する問題の本質が、実は面子の問題であることが多々あります。相手の反応に戸惑うことがあったら、その人の面子を潰していないかを考えてみると、理解できることがあるかもしれません。
2. 社内でのビジネス習慣
まず、赴任先やグループ会社など、中国人と一緒に働く上で覚えておきたいビジネス習慣をご紹介します。
2-1. ランチタイムの重要性
中国人は食事を大切にする習慣があり、ビジネスでも11時半から13時半くらいまでのランチタイムを重視します。背景として、中国では健康な身体を維持するには、きちんと食事を取らなければならないという感覚が日本よりも強いことが挙げられます。「民は食を天(一番大切なもの)とする(民以食为天(mín yǐ shí wéi tiān))」という慣用句があり、食べることは空腹を満たす以上の意味を持っています。
日本でも食事は大切ですが、ビジネス上のランチタイムは比較的軽視される傾向があるのではないでしょうか。会議が長引くとランチライムをずらしたり、最近ではアポが取りやすいという理由で商談を12時台に入れることもありますが、その感覚を中国に持ち込むのは危険です。
2-2. 知ると役立つ社内でのビジネスマナー
上記で挙げた以外にも、知っていると役立つマナーをご紹介します。
男性が相手の配偶者(女性)の容姿を褒めてはいけない
中国では未婚・既婚を問わず、女性の容姿を褒めることはその人に好意があると理解されてしまいます。中国人男性の配偶者を「綺麗な方ですね」とうっかり褒めてしまうと、相手は挑戦状を叩きつけられたと感じかねないので注意しましょう。同様に、男性から女性に握手を求めるのもNGです。
なお、この意識は20代の若者を中心に徐々に薄れてきているようです。若者同士であれば、あまり気にしなくてよいかもしれません。相手が中高年以上の場合は注意するようにしましょう。
タバコは火をつける前に相手に1本差し出す
自分が喫煙をするときは、タバコに火をつける前に相手に1本差し出すのがマナーとされています。また、相手が喫煙をするときは逆に1本差し出されるため、自分のタバコを出さずに待っておくのがよいでしょう。非喫煙者はその旨を伝えれば受け取る必要はなく、相手も不快に思うことはないのでご安心ください。
なお、こちらのマナーも、喫煙に対する意識の変化から、若者を中心にあまり見られなくなってきているようです。
仕事を手伝うという感覚はあまりない
中国では、自分に与えられた仕事は自分のものであり、一人でやり通すという認識が一般的です。相手から声をかけられた場合は別ですが、頼まれていないのに仕事を手伝うことはあまりしない方がよいでしょう。「自分の仕事を横取りされた」「面子を潰された」と感じられてしまう可能性があります。
ここまで、中国人と一緒に働く上でのビジネスマナーをお伝えしました。日本人同士の場合は気遣いと捉えられることも、海外では真逆の意味を持ってしまう場合があります。反対に、赴任先で日本人の感覚では不可解なことが起こっても、文化的背景が異なることを意識しておけば、冷静に対応ができるかもしれません。
3. 商談に関するビジネスマナー
ここからは、対社外の中国人と接する際に覚えておきたいビジネスマナーをご紹介します。
3-1. 名刺交換
業種や年代にもよりますが、現在では紙での名刺交換の代わりに、WeChat(微信)という中国版LINEを交換することが多いです。実際に、ライトワークスの中国人スタッフや中国駐在員を対象としたアンケートの回答をご紹介します。
「中国企業は名刺交換ではなく、WeChatの交換が圧倒的に多いです。日本人からみると、初対面のビジネス上でSNSアカウントを交換することは不思議だと思われる方が多いと思いますが、中国ではごく普通のことです。
また、中国人宛に訪問した際に、こちらから紙の名刺を渡しても、名刺の交換ではなく、その代わりにWeChatで交換しましょうと言われることも多いです。WeChatを交換した後、相手から電子版の名刺を送ってくるケースがほとんどです。
日本は名刺文化が非常に強い国であり、商談の席では「テーブルの上に綺麗に並べる」など、名刺を丁寧に扱うことがビジネスマナーとなっていますが、中国ではそうではありません。(中国人スタッフ 20代男性)」
しかし、WeChatが浸透するあまり、別の問題が出てきています。
「WeChatはビジネスシーンでも浸透しているのですが、契約に関することまでWeChatで話をしている人も多いようで、各社課題感を持っています。直近はサイバーセキュリティ法施行などの影響で、企業側のセキュリティ意識も高まってきています。(中国駐在員 30代男性)」
こうしたセキュリティ上の問題に対応するため、企業版WeChatを採用する企業が増えています。WeChatの有料版企業アカウントは、社内での情報共有や顧客とのやりとりを会社が管理できて、会話の流出を防げるほか、退職した従業員のログの持ち出し対策もできます。
3-2. 握手
中国では、初対面の時や久しぶりに会った時など、挨拶とともに握手をすることが多いです。しかし、一時は新型コロナウィルスの影響で握手をする場面が少なくなり、代わりに「拱手」をしている人がみられたそうです。
「拱手」とは、右手の拳を左手で包む動作で、中国ならではの辞儀です。相手に対して感謝や依頼の気持ちを表します。平時にはあまり意識する必要はありませんが、こうした代替のマナーも覚えておくとよいでしょう。
日本では厳格なマナーが敷かれている名刺交換も、世界各国で全く扱いが異なるようです。中国のビジネスマナーに興味を持ったことをきっかけに、異文化コミュニケーションを見据えて、世界各国のビジネスマナーを調べてみるのもおすすめです。
4. 接待に関するビジネスマナー
パナソニックやホンダなど、日本には接待を原則禁止している企業が多数ありますが1、中国ではクライアントと良好な関係を築き、円滑にビジネスを進めることを目的として、現場レベルの親睦会とは別に、重役クラスを招いた接待(宴会)を開く慣例も残っています。
宴会には、本来の目的以外にも、以下のようなメリットが期待できます。
(1) 宴席の並び方で、役職だけでは判断できない真の序列がわかる場合がある
(2) 商談ではあまりお目にかかれない、トップ(決裁権者)と直接話せる
席次について
日本同様、入り口から反対側の奥の席が最上席となっています。中国の伝統的なマナーとしては、費用を全額負担するホストが着席するのですが、最近ではゲストのトップが着席する場合もあるようです。ホスト側の場合は、事前にゲスト側の担当者に相手方の席次を決めてもらった方がよいでしょう。ゲスト側の場合は、指示があるまで座らずに待っていた方が無難です。
乾杯について
宴会の最初と最後に乾杯と挨拶を行います。乾杯後も、一人でお酒を飲むのはマナー違反とされています。一人で飲んでいると、周りに失礼なだけでなく、「この宴会に不満があるのか」「早く帰りたいのか」と、クライアントを不安な気持ちにさせてしまうので注意しましょう。
お酒を飲む場合は、自分同様に乾杯する相手を探している人がいないかを確認し、目を合わせて「乾杯!」と言って一気に飲み干します。お酒が飲めない方は事前にその旨をはっきりと伝えておけば、失礼に当たりません。
食事は少し残すのがマナー?
中国の食事に関するマナーとして代表的なものが、「食事は少し残す」ということが挙げられます。しかし、中国のフードロス問題が世界的に有名となるにつれて、意識改革に向けた動きが見られています。
2013年に中国全土で食べ残し禁止キャンペーン「光盤行動(光盤=皿を空にするの意味)」が打ち出されましたが、あまり浸透していませんでした。2020年、いよいよ習近平国家主席が「食べ残し禁止命令」を出し、飲食業界がメニューを改善したり、注文の仕方を工夫するなど、フードロス問題解消に向けて本格的な取り組みを始めています。2
お礼は当日中に
ゲスト側の場合、接待のお礼は当日中に済ませるのがマナーです。
前述の通り、中国人は食事の時間を大切にします。大切な時間を共に過ごし、相手の好みや心を知ることで、友好関係を築いていく事ができ、よりよいビジネスの結果にも繋がります。
5. まとめ
この記事では、日々進化していく中国の文化を反映した、実践ですぐに使える中国の基本的なビジネスマナーをご紹介しました。
ビジネスマナーを理解するために、中国の特徴的な文化として「面子をとても大切にする」傾向があるということを知る必要があります。中国人と仕事を進める上で直面する問題の本質が、実は面子の問題であることが多々あります。相手の反応に戸惑うことがあったら、その人の面子を潰していないかを考えてみると、理解できることがあるかもしれません。
赴任先やグループ会社など、中国人と一緒に働く上で覚えておきたいビジネス習慣・マナーは以下の通りです。
・ランチタイムを重視する
・男性が相手の配偶者(女性)の容姿を褒めてはいけない
・タバコは火をつける前に相手に1本差し出す
・仕事を手伝うという感覚はあまりない
日本人同士の場合は気遣いと捉えられることも、海外では真逆の意味を持ってしまう場合があります。反対に、赴任先で日本人の感覚では不可解なことが起こっても、文化的背景が異なることを意識しておけば、冷静に対応ができるかもしれません。
対社外の中国人と接する際に覚えておきたいビジネスマナーは以下の通りです。
・名刺交換
2020年現在、紙での名刺交換の代わりに、WeChat(微信)という中国版LINEを交換することが圧倒的に多い。
・握手
中国では、初対面の時や久しぶりに会った時など、挨拶とともに握手をすることが多い。
セキュリティ意識の向上により、業務上の連絡については企業版WeChatを採用する企業も増えています。有料サービスですが、会社側が会話のログを管理し、流出を防ぐことができます。
当ライトワークス社の中国子会社・来宜も、企業版WeChatのカスタマイズや活用のご相談に対応しています。
接待に関するビジネスマナーは以下の通りです。
・席次は日本同様、入り口から反対側の奥の席が最上席となっている。
・乾杯は宴会の最初と最後に挨拶とともに行う
・食事は少し残すのがマナーとされていたが、中国のフードロス問題が世界的に有名となるにつれて、意識改革に向けた動きが見られている。
・お礼は当日中にする
郷に入れば郷に従えという言葉通り、文化の異なる地でビジネスをスムーズに進めるには、その地ならではのマナーを知ることが重要です。しかし、それ以上に、相手の文化的背景を想像し、敬意を持って接することが何よりも大切です。友好を深め、信頼関係を結ぶことができれば、あなたにとって非常に心強いパートナーとなってくれることでしょう。
- 本名 信行、羅 華(2018)『Q&Aでわかる 中国人とのつき合いかた』大修館書店.
- 筧 武雄、上村ゆう美(2006)『中国とのつき合い方がマンガで3時間でわかる本』明日香出版社.